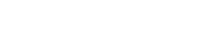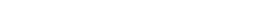チームボックスの推進する女性リーダー育成プロジェクト「Project TAO(プロジェクト タオ)」。
社会や組織の変化を恐れず、生き生きと活躍できる女性リーダーの輩出促進を目的とした取り組みです。
「TAO」に込められた意味のひとつは「道」。私たちが進むべき道を学ぶケーススタディとして、リーダーシップを発揮する女性にお話を伺い、2つ目の意味である「先達からのタスキがけ」として次世代へとバトンを渡します。
今回は、立教大学経営学部の客員准教授である藤澤 広美さんに話を伺います。
民間企業での実務経験を経てアカデミアの道へ進み、キャリア教育や人材マネジメントの研究に取り組んできた藤澤さん。現場と大学、教育と支援を行き来しながら、どのようなリーダーシップを発揮してきたか、語っていただきます。
立教大学経営学部 客員准教授・博士(マネジメント)
藤澤 広美 氏
島根県生まれ、岡山・山口・広島で育つ。大学卒業後、HR系ベンチャー企業に入社し、コンサルティング業務に従事。メーカー系販社で法人営業を担当しながら社会人大学院(修士課程)へ進学。修了後は大学でキャリアカウンセラーを務めながら博士課程に進学。2017年より立教大学 大学教育開発・支援センターFD(Faculty Development)部門の助教、2020年より経営学部助教、2025年より現職。ZEN大学 知能情報社会学部の客員講師も兼務。専門はキャリア教育・人材マネジメント。「学びとキャリアを科学する」をテーマに、実践・研究を往還しながら活動している。
現場で育む、キャリアとリーダーシップの実践知
瀬田 千恵子(以下、瀬田):藤澤先生が携わっている社会人大学院のLDC(リーダーシップ開発コース)で、院生として授業を受けた経験があります。先生がいらっしゃると場の雰囲気がとても明るくなり、心理的安全性を感じていました。今日は、藤澤先生らしいリーダーシップについて、お聞きできればと思います。まずは、現在のお仕事について紹介いただけますか。
藤澤 広美(以下、藤澤氏):ありがとうございます。現在は立教大学経営学部に所属し、主に社会人大学院のLDCを担当しています。LDCは、働きながら学び直せるオンラインコースで、多様なバックグラウンドを持つ社会人が院生として学んでいます。「人と組織」に関する理論と実践の往還を大切にしながら、自身のリーダーシップを開発していくのが特徴です。私は2020年からコース運営や基幹科目、専門であるキャリア科目を担当し、オンラインだからこそできる工夫を取り入れながら、院生の学びを支援しています。
また、2025年からZEN大学でフルオンデマンド形式のキャリア教育科目を担当しています。自己理解の方法やキャリア構築に関する理論などを伝えることを通して、大学教員としての実践に取り組みながら、研究活動も行っています。

瀬田:藤澤先生が現在のお仕事に至るまでのキャリアの変遷を教えてください。なぜ教育や研究の道に進まれたのでしょうか。
藤澤氏:振り返ると、「社会をより良くしたい」という想いが、教育や研究に進んだ原点だったと思います。
新卒でHR系のベンチャー企業に就職し、キャリア支援の仕事に携わりましたが、利益優先の場面で「本当に相手のためになっているのか」と疑問を感じることがありました。また、自分自身が職場や環境に違和感を抱き、不本意な離職を経験したことで、人や組織に対する問題意識が芽生えていったのです。
「もっと本質的に人や組織を理解したい」と思い、大学院(修士課程)に進学しました。アカデミックな場なら利益にとらわれず、多くの人たちの成長やキャリアに正面から向き合えるのではないかと感じたからです。
瀬田:現在は大学生を対象としたキャリア教育の研究にも取り組まれているとお伺いしています。若い世代にアプローチしようと思われたのはなぜですか。
藤澤氏:修士課程では若年労働者を研究対象としていましたが、大学生のキャリア支援に携わるなかで、「もっと早い段階での支援が必要だ」と強く感じるようになりました。
大学時代は自分の価値観に気づき、将来を考え始める大切な時期です。このタイミングで適切なキャリアガイダンスが受けられれば、社会に出たあとも自らの選択に納得しやすくなると考えています。
もちろん、高校や中学校といった、より早いキャリア教育も重要ですが、いまは現場で問題意識を感じた大学生に焦点を当てています。
瀬田:大学生はキャリアが将来の進路と結びついてくる時期ですよね。久しぶりにキャンパスに来ましたが、若い人たちの活気を感じました。
藤澤氏:そうですね。社会人教育も意義深いですが、学生はまだ思考や発想が柔軟で、成長が目に見えてわかりやすいんです。たとえば、1科目の授業でも視野が広がり、行動が変わることがあります。
そして彼らは、これからの社会を担っていく世代です。若い人たちのキャリア形成を支えることは、個人だけでなく社会全体への貢献にもつながると感じています。
瀬田:藤澤先生にとって、これまでのキャリアのなかで最大の岐路はいつでしたか?
藤澤氏:いくつか転機がありましたが、最も大きな影響を受けたのは修士課程時代に指導教員の先生と出会ったことです。その先生との出会いが、アカデミアの道を開いてくれました。
もともとは企業で専門性を高めていくつもりでしたが、ちょうど結婚などのライフイベントが重なり、自分の働き方を見直していた時期でもありました。そんなときに先生に相談したところ、3つの選択肢を提示してくださったんです。
1つ目は実務家、2つ目は「実務家×専門家」としてのハイブリット型、3つ目は教育や研究の道。そのうえで、「あなたは若い人を支援することに向いていると思う」と言ってくださいました。
その言葉を聞いたとき、「若者がいきいきと働ける職場づくり」について研究してきたからこそ、若い人と一緒に考えたり、支援したりすることに大きなやりがいを感じられそうだと気づき、未来のイメージが一気に広がりました。
そこで思い切って企業を辞め、大学のキャリアカウンセラーに転身しました。この一歩が、今につながる大きな転機になったと思います。
気づき、支え、つないでいく、私らしいリーダーシップ
瀬田:LDCにはコース開設当初から携わられていますが、どのようなリーダーシップを発揮してきましたか?
藤澤氏:LDCには立ち上げ直後から運営に加わり、学部長の山口和範先生、リーダーシップ研究者の石川淳先生、コース主査の中原淳先生、事務局、そして当時助教だった私という体制でした。構想自体は、私以外のメンバーによって練られていたため、私は運営が始動するタイミングで参画した立場でした。
そのため、最初は背景や文脈を十分に把握しきれておらず、苦労する場面もありました。日々の実務や運営陣との対話を通じて、自分に求められている役割を手探りで見出していきました。いま振り返るとICT活用や人の動き・感情に敏感に気づけること、さりげないサポートなどが私らしいリーダーシップのスタイルだと捉え、チームの中で発揮できるようになったと感じています。
瀬田:受講者として、藤澤先生の細やかな配慮をいつも感じていました。

藤澤氏: ありがとうございます。LDCのスタートはちょうどコロナ禍と重なり、予定していた対面授業を急遽オンライン授業に切り替える必要がありました。技術面のサポートを自主的に引き受け、他の先生方の授業支援をしながら、受講生の様子の把握や授業の改善提案などにも積極的に取り組みました。
このような“支援型”のリーダーシップが、自分のスタイルに合っていると感じています。サポートを通じて、コース全体の構造や課題が見えやすくなった点も、大きなメリットでした。
瀬田:錚々たる個性のある先生方が抽象度の高いアイデアとして提供しているものを、つないで具体化してくださったのは藤澤先生だったと思っています。他の先生方も頼りにしていたでしょうし、藤澤先生がいるからまとまった面があったのではないでしょうか。
藤澤氏:裏方として動くことが多いので、受講生からそのように見えていたとしたら、とてもうれしいです。実際、先生方のアイデアやビジョンを現場でかたちにしていく“実行部隊”のような役割を担っていた感覚はあります。こうした場で、理論と実践を行き来しながら取り組めること自体が、私自身にとっても学びの多い、ありがたい環境だと日々感じています。
瀬田:他の先生方から見ると、藤澤先生のリーダーシップは支援型だったと思うのですが、実行という面を切り取れば、先頭に立ったリードをされていました。
藤澤氏:確かに、実行のフェーズでは、結果的に前に立つこともありました。リーダーシップのかたちは、文脈や関係性によってその見え方が変わるものだと思います。そういう意味でも、「支援」と「実行」は対立するものではなく、両立できるスタイルとして、これからも大切にしていきたいですね。
瀬田:コロナ禍はイレギュラー続きで混乱もあり、みんなで力を合わせなければいけない場面も多かったのではないでしょうか。どのように乗り越えましたか?
藤澤氏:当時はまさに時間との勝負でした。大学の方針がでる前から事務局と連携してオンライン化の準備を始め、必要な手順やサポート体制を整えていきました。複数のオンライン研修やセミナーにも参加し、授業運営に活かせそうなものを吸収していきました。
準備期間は2週間ほどでしたが、チーム一丸となって乗り越えた感覚があります。
瀬田:2週間でそこまで!やると決めてからの底力やタフネスも藤澤先生の持ち味ですね。
藤澤氏:ありがとうございます。もともと課題を見つけて改善していくのが好きでした。中学生の頃から授業中に「ここはこうしたほうが分かりやすいかも」と先生に提案していたくらいです。もちろん、歓迎してくれる先生もいれば、「授業の邪魔をしないで」と煙たがられることもありました(笑)
瀬田:まさに藤澤先生らしさですね。クライアントと話していると、上下関係がある中で、部下が上司に、あえて批判的な視点をアイメッセージで伝えることは難しいと感じている方がとても多いです。一方で、上司側も本当は部下やチームメンバーに「助けてほしい」と思っていても、プライドや恥の意識が邪魔してしまい、さらけ出すことが苦手だとおっしゃることがあります。そんな中、藤澤先生は子どもの頃から自然に「自分の意見を伝える」ことを実践されてきたんですね。
藤澤氏:親によると、物心つく前から「嫌なことは嫌」と言う子だったようです(笑)。性格的な部分もあるかもしれませんが、大切なのは「何のために伝えるか」という目的意識だと思っています。
チームで同じゴールを目指しているなら、気づいたことを共有するのは組織全体のためですよね。上下関係に遠慮せず伝えることが、結果的にチーム全体の成果につながると考えています。
また、どんな立場の人も「助けて」と言っていいと思うんです。弱さを見せることは恥ずかしいことではなくて、むしろ信頼関係を深めるために欠かせない行為です。だからこそ、アサーションや自己開示はとても大事だと考えています。
瀬田:そうした経験や姿勢が、LDCの運営にも生かされたんですね。これまでもお聞かせいただいていますが、ご自身の「自分らしさ」はどこにあると感じますか?
藤澤氏:ひとことで言うなら、「つなぐこと」だと思います。
異なる世代や立場の人の思いをつなぐこと、新しいステージへの移行を後押しすること、人と人、人と機会をつなぐこと。そうした“接続役”であることが、自分らしさだと感じています。
たとえば、「この二人が出会ったら何かが生まれそう」と感じたら、ご縁をつなげたくなるんです。そういう直感を大切にして、これからも「つなぐこと」を大事にしていきたいです。
主体的な学びを促す、キャリア教育の新しいかたち
瀬田:2025年からはZEN大学でもキャリア教育を担当されているそうですね。立教大学とは違う点で、工夫されていることはありますか?
藤澤氏:はい。ZEN大学では「フルオンデマンド形式」の授業を担当していて、あらかじめ収録された15回分の授業を、学生が四半期ごとに自分のペースで視聴しながら学ぶスタイルです。画面越しでも伝わるように構成やテンポ、言葉の選び方などに工夫が必要になるため、制作チームと連携しながら映像コンテンツを丁寧に設計しました。
また、学修環境にばらつきがある学生でも取り組みやすいよう、紙やタブレットなど身近なツールで行える個人ワークも取り入れています。「誰でも、どこでも、自分のペースでキャリアを考えられる」場づくりを意識しています。主体的な学びをどう支えるかは、オンライン時代のキャリア教育にとって重要なテーマです。

瀬田:ZEN大学では先生が教える側で、スタッフがサポートしてくれる体制なんですね。LDCの運営も経験されてきた藤澤先生にとって、両方の立場から場作りを考えられるのは大きな強みですね。
藤澤氏:ありがとうございます。支援する側・される側、大学・現場、教育・生活など、さまざま視点があるからこそ気づけることがあると実感しています。いろいろな立場を経験してきたことが、自分の視野を広げてくれました。
たとえば、ZEN大学ではオンデマンド授業にアニメーションを取り入れることで、「一緒に学んでいる感覚」や「人の温かさ」を感じてもらえるよう工夫しています。学生がキャラクターに親しみを持てるように設計していて、どんな反応があるか楽しみです。
瀬田:キャリア教育に温かさを感じてもらいたいという想いも、藤澤先生らしさですね。
藤澤氏:キャリアは進路選びだけではなく、「どう生きたいか」という感情や想いが深く関わるものです。だからこそ、心が動くような心理的なアプローチを大切にしながら、キャリア教育を届けていきたいと思っています。
瀬田:実は、私も社会人研修のほかに、慶応義塾大学の体育会男子バスケットボール部でリーダーシップやチームビルディングの支援もしています。対象が変わると、私たち提供する側の捉え方や伝え方も変わってきますよね。藤澤先生は、社会人と学生に教えることの違いをどう感じていますか?

藤澤氏:そうですね。社会人は経験があるぶん話の前提が共有しやすく、伝えやすいと感じます。一方で学生は、社会経験が少ないので、抽象的な話が実感しづらい傾向があります。そのため、身近な話題を例にして「自分ごと」にして捉えてもらえるように意識していますね。
瀬田:今の学生は、以前と比べると基礎能力がとても高いですよね。物事の受け取り方や学び方のセンス、AIを活用するスペックが揃っていることの違いも大きいです。
藤澤氏:本当にそうですね。まさに「AIネイティブ世代」だと感じます。SNSやオンラインゲームなどで顔を知らない相手と自然につながることに慣れていて、私たちの世代とはコミュニケーションの形も異なります。だからこそ、教える側も彼らの価値観や背景を理解しながら関わる姿勢が求められると感じています。
瀬田:キャリア教育のあり方も、学ぶ側の変化に合わせて進化しているということですね。
藤澤氏:まさにその通りです。キャリア教育そのものも変化し続けていますし、受け手の感覚や価値観も日々変わっています。その変化に寄り添いながら、柔軟に届けていくことが、これからのキャリア教育には欠かせないと思っています。
日々の積み重ねが、自分らしさを形づくる
瀬田:ときには仕事がうまくいかない時もありますよね。困難な状況に陥ったとき、藤澤先生は自分をどのようにモチベートしていますか?
藤澤氏:もちろん、仕事がうまくいかないと感じることもあります。そんなときは原点に立ち返り、「これは自分がやりたくてやっていることだ」と思い出すようにしています。そして、家族や子どもの存在が自分にとって大きな支えになっていることに改めて気づかされます。
対人関係でうまくいかないときは、まず相手の状況や背景を想像し、そのうえで相手の想いや背景を推察したうえで、自分のスタンスを調整することもあります。その一方で、相手の感情に振り回されないようにすることも心がけています。

瀬田:藤澤先生はイメージする力がとても豊かですよね。人の感情を考えて全体を調整するところも藤澤先生らしさだと思います。意思決定の際はどのように判断されていますか?
藤澤氏:10年後、20年後の「ありたい姿」を描いたうえで、タイミングを見て動くようにしています。選択肢を整理し、「現実的かどうか」「目的に沿っているか」を基準に判断します。夫や友人に話すことで考えや優先順位を整理されることもありますが、最近はAIと対話しながら実行プロセスの精度を高めることもあります。
瀬田:3年後などではなく、だいぶ長いスパンで考えているんですね。決断の際、迷うこともありますか?
藤澤氏:もちろんあります。家族の状況や子どもの成長など、不確実な要素が多いなかで、日々迷います。その都度立ち止まりながら選択肢を見直したり、優先順位を入れ変えたりしています。大学教員や研究者として理想的なキャリアパスもありますが、型にはまらず、状況に応じた選択を大切にしたいと思っています。
瀬田:キャリアを専門にされているからこそ、ご自身の人生をとてもフレキシブルに捉えていらっしゃいますね。そして信念もしっかりお持ちだと感じます。
2023年には博士号も取得されています。お子さんが生まれて育児が大変な時期だったと思いますが、同時並行でよく成し遂げられましたよね。人生の大きなイベントが重なったときの乗り切り方はありますか?
藤澤氏:「やりきる」と決めて、限られた時間で集中して取り組みました。計画的に進めつつ、想定外の出来事にも柔軟に対応するようにしていました。
瀬田:目標に向かう行動と調整力の両方が大事なんですね。
藤澤氏:その通りですね。長期的な視点と、目の前のことに誠実に向き合う姿勢のバランスを大切にしています。
ただ実際には、博士論文執筆中に産休・育休はなく、生後間もない子どもを膝に寝かせながら作業をしたり、寝かしつけたあとにパソコンに向かったりする日々が続きました。産後の免疫力低下もあり、体調を崩して入院・手術も経験しました。
結果的に博士号取得の目標時期から半年遅れましたが、「誤差の範囲」と捉えました。目標は、状況に応じて柔軟に変えてよいことを前提に持ちながら、いまは無理せず家族のために健康第一で過ごしたいと思っています(笑)
瀬田:そのメリハリも大切ですよね。覚悟を決めて集中するときと、ご家族との時間を大切にする柔らかさの両方があるのは素敵です。
最後に、藤澤先生のように人生を進めたいけれど、なかなかうまくいかないと感じている方へ、メッセージをいただけますか。
藤澤氏:私自身、まだ自分のことをすべて理解しているわけではありません。でも、「うまくいかないな」と感じている方は、まだ知らない自分が残っている可能性もあります。言い換えれば、自分を試したことがないだけかもしれません。
小さな一歩でも、新しいことに挑戦することで“自分らしさ”が見えてくると思います。自分の感覚を大切にしながら、少しずつ輪郭を描いていってください。
そうした日々の積み重ねが、次のチャレンジにつながり、自分らしいキャリアを形づくっていく。私はそう信じています。
瀬田:本当にそうですね。藤澤先生がなぜここまで頑張ることができるのか、芯のある強さがあるからこそなんだということを実感できた、とても充実したお時間でした。ありがとうございました!
コラム
Column
各サービスについての資料請求はこちら
Download documents
各サービスや講演、取材についての
お問い合わせはこちら
お問い合わせはこちら
Contact