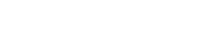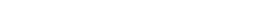チームボックスの推進する女性リーダー育成プロジェクト「Project TAO(プロジェクト タオ)」。社会や組織の変化を恐れず、生き生きと活躍できる女性リーダーの輩出促進を目的とした取り組みです。
「TAO」に込められた意味のひとつは「道」。私たちが進むべき道を学ぶケーススタディとして、リーダーシップを発揮する女性にお話を伺い、2つ目の意味である「先達からのタスキがけ」として次世代へとバトンを渡します。
今回は、国立スポーツ科学センターのスポーツ医学研究部門の産婦人科医である能瀬さやかさんにお話を伺います。能瀬さんは産婦人科医としてスポーツ医学に携わり、女性アスリートの健康管理やパフォーマンス向上に取り組んでいます。2017年には東京大学医学部附属病院に国立大学病院初の「女性アスリート外来」を開設しました。前例がない産婦人科医とスポーツドクターとの両立や、未踏の道を切り開いてきた軌跡について、語っていただきます。
国立スポーツ科学センター スポーツ医学研究部門 産婦人科医
能瀬 さやか 氏
1979年 秋田県生まれ、青森県八戸市育ち。北里大学医学部卒業後、2006年に東京大学産婦人科学教室入局。
国立スポーツ科学センターなどを経て、2017年より東京大学医学部附属病院女性診療科・産科、国立スポーツ科学センター婦人科 非常勤、浜田病院 非常勤。
2023年から国立スポーツ科学センター スポーツ医学研究部 産婦人科医、浜田病院女性アスリート外来非常勤
日本産科婦人科学会専門医、日本スポーツ協会公認スポーツドクター、日本パラスポーツスポーツ協会公認障がい者スポーツ医。
産婦人科とスポーツドクターの架け橋となる存在に
瀬田 千恵子(以下、瀬田):私達チームボックスが推進する女性リーダー輩出促進プロジェクト「Project TAO」の「TAO」に込められた意味のひとつは「道」です。人生は選択の連続で、能瀬さんにとっても産婦人科医とスポーツドクターを両立していく中では、さまざまな選択に向き合ってこられたと思います。まず、それらがどのようなご経験であったかを教えてください。
能瀬 さやか(以下、能瀬氏): 産婦人科医とスポーツドクターを両立することになった理由はいくつかあります。父が産婦人科医だった事もあり、ずっと産婦人科に興味を持っていました。また、小さい頃から熱中していたバスケットボールで怪我をしたことから、スポーツ医学にも関心がありました。
医学部生の頃は、スポーツ医学といえば整形外科がメインだったので、整形外科と産婦人科のどちらの道に進むか悩み続けていました。そんな時に、公衆衛生の先生の研究室で「女性アスリートには無月経など月経の問題がある」という記事が載っているパンフレットを見つけたんです。それを見てハッとして…産婦人科に行ったらスポーツ医学のことはできないと思っていましたが、女性アスリートの問題があるなら、スポーツ医学にも産婦人科医として関われるのではないかと考えるようになりました。その時に産婦人科医になることを決めました。
2012年に初めて国立スポーツ科学センターに、5年間の任期で勤務することになりました。
その時は自分が若いこともあり、産婦人科から離れてスポーツ医学にどっぷり関わることに多少の不安や葛藤がありました。でも任期を終えて東大病院に戻った際に、自分が周囲の産婦人科医からどう見られているかを初めて知ったんです。「スポーツ医学を専門にして、アスリートの診療をしている能瀬」だと認識されていることに気づきました。「自分はそう見られているんだ!」というのもあって、少しずつ意識が変わっていきました。2023年に再び国立スポーツ科学センターから産婦人科医としてお声がけいただいた時には、「こういうチャンスがある産婦人科医はそんなにいない、自分だからこそできることをしたい」と、すぐに赴任を決断しました。1度目に行った時は不安と葛藤がある中でしたが、2度目は「これをやるぞ!」という想いで行きました。

瀬田:国立スポーツ科学センターへの赴任は、1度目と2度目で、心の持ちようにも変化があったのですね。
能瀬氏:そうですね。経験やキャリアを積んだことで、変化がありましたね。
瀬田:産婦人科医としてスポーツ医学に携わった成功体験が自信につながったということでしょうか?
能瀬氏:そうですね。産婦人科医としてひと通りの診療経験を積んで、アスリートの診療をしていることも周囲に認知されるようになっていたからだと思います。産婦人科医になり立ての頃に、大学の教授にアスリートの診療をしたいと話したら、「産婦人科でスポーツ医なんて何を言っているんだ」という戸惑いの目を向けられた感じでした。今では、産婦人科医の間でも「女性アスリート特有の課題に関わる必要がある」という認識が少しずつ広がり、スポーツ医学側でも「産婦人科の視点が重要だ」と理解されるようになりました。
瀬田:まさに橋渡しの役割を果たされたんですね。
能瀬氏:産婦人科とスポーツ医学の両方の分野に携わることができたのは本当にラッキーだったなと思います。これまで女性アスリートの診療や支援に関わってこられた先生方のお蔭だと思います。
女性アスリートのライフイベントの捉え方に変化も
瀬田:以前、このProject TAOの対談企画で、サッカーの川澄奈穂美選手にインタビューさせていただきました。男女の格差のお話を伺った際に、女子選手も格差があることが前提になっていて、スポーツ界特有のしがらみが結構あるのかもしれないという印象を持ちました。
能瀬氏:スポーツ医学は関わっている人が限定されているので、私がスポーツ医学に関わり始めた頃は、閉鎖的だったように思いますが最近はとてもオープンになってきていると思います。
瀬田:川澄選手のお話からは、女子選手の立ち位置や待遇面でも、日本では女性アスリートが男性に比べて不利な状況にあると感じました。女性のアスリートがもっと声を上げていくには、どこを変えていけばいいとお考えですか?
能瀬氏:昔は選手たちの声を私たちが聞く機会はありませんでしたが、今はSNSが普及して、アスリート自身が直接発信できるようになっています。以前よりは、月経の話題なども積極的に発信する選手が増えていると感じますね。
瀬田:今は、「出産しても競技を続けたい」と考えるアスリートは多いのではないでしょうか?
能瀬氏:そうですね。以前は、妊娠・出産をするとアスリートとしてのキャリアが終わってしまう、という認識が強かったと思います。最近は、出産後も競技に復帰し、トップレベルで活躍し続ける選手が増えてきました。
国立スポーツ科学センターでも、今年度から産後競技復帰に向けた支援や研究に取り組んでいます。これまでは、妊娠中や産後のデータに基づいてトレーニングをサポートしていましたが、現在は可能な範囲で妊娠前からデータを取り、妊娠中から産後1年までを継続してサポートする体制を整え始めています。卵子凍結の希望も増えてきていますね。

瀬田:相談に来られた選手には、スポーツとの両立について、どのようなアドバイスやサポートをされるのでしょうか?
能瀬氏:競技復帰を決めている選手の場合、妊娠中もできるだけ妊娠前の身体機能や運動パフォーマンスを落とさないようにサポートを行います。具体的には、トレーニング、科学、栄養、心理、婦人科、整形外科など、さまざまな分野の専門家がまず評価を行い、評価結果に基づいて妊娠中や産後のトレーニング指導を行っています。
瀬田:さまざまな専門家が集まってチームで動かれているということですが、その中で能瀬さんはどのようにリーダーシップを取られていますか?
能瀬氏:私はプログラムリーダーという立場で、全体のことを考える役割を担っています。多くの人が関わると、分野ごとに異なる視点や意見が出てくるので、共有する場を設けるように意識しています。かなり多くの方が関わっているので全員集まれる機会は少ないのですが、同じ方向に進むためには、しっかりとコミュニケーションを取ることが大切です。オープンな場でのコミュニケーションが効果的な場合もあれば、個別で話す方がいい場合もありますね。
瀬田:アスリートの身体に関わることですし、情報の取り扱いもセンシティブになりますよね。
能瀬氏:選手と私が話す際は、診察室で個別にプライバシーを守りながら話すようにしています。スタッフでミーティングをする時は、みんなで共有するべきか、専門分野の方だけに話すべきかを使い分けが必要な内容もあります。
瀬田:私も今日、お話しをさせていただいてすごく感じたのですが、能瀬さんとお話ししていると、ついつい話したくなってしまいますね。本当に信頼できる方で、頼れる先生だからこそだと思います。アスリートとの関わりの中でも「信頼関係」がとても大切なのでしょうね。
能瀬氏:「誰にも言わないでください」と言う選手も多いですし、わざわざ周りに同じ競技の選手がいない時に受診する選手もいます。選手たちは、弱さを見せたくないという思いを強く持っているので、私に限らずチーム等に関わっていない、ある意味第三者である医師等にはいろいろお話できることもあるのだと思います。
一度の受診で話してくれる選手ばかりではなく、何度かの診察を経て、ようやく本音を話してくれることもあります。例えば、月経について全く関心がない選手もいれば、ピルや生理痛について詳しく知りたい選手もいます。選手の雰囲気から、どれくらいの情報を求めているのかも察するようにしています。
瀬田:スポーツに真剣に向き合うアスリートの方々は、それぞれ自分自身の信念や軸となるものを持っていることが多いと思いますが、中にはそれが定まってない方もいらっしゃると思います。見極めるためには、コミュニケーションが大切なのではないでしょうか。
能瀬氏:受診時と外での様子が異なることもありますし、その場では理解してくれたように見えても、後から問い合わせが来て「実は理解されていなかった」と気づくこともあります。
瀬田:それは人材育成にも通じる部分がありますね。聞いているときは理解しているように見えても、いざ実践となると「自分ごと」になっていない場合が多々あります。能瀬さんのように、人生を変えるような支援をされる立場ではなおさら、相手をしっかり観察し、関係性を築くことが大切ですね。
能瀬氏:同じ話をしても、受け取る側の理解度はさまざまです。だからこそ、チームや目の前の相手とのコミュニケーションが大切だと考えています。
「自分ごと」として捉えてこそ、自分の人生を歩むことができる
瀬田: 2024年はパリオリンピックも開催され、大きなスポーツイベントが続いています。昨今の傾向として、スポーツのキャリアが短期的なものから中長期的なものへと変遷していると感じられます。
能瀬氏:ライフプランを見据えてキャリアを考えながら競技生活を送る選手もいれば、そうでない選手もいます。例えば、婦人科の健康管理に関しても、自分で記録してセルフケアできている選手と、スタッフに聞かないとわからない選手もいます。リテラシーは選手によって全然違いますね。
医学的な視点で婦人科の立場から言うと、自分の体に向き合っている選手ほど、自己認識が高く、自分の体やメンタルの状態を理解しています。自己を認識できていない人は知識を得ようと思わないですし、そもそも受診をしていないと思います。

瀬田:自己認識の高さは、スポーツのパフォーマンスにも直結しますよね。
能瀬氏:そうなんですよね。ホルモン周期がパフォーマンスに影響するという研究がされていますが、最近注目されてるのは、月経に関連する症状です。例えば、月経痛やPMS等の症状がパフォーマンスに影響するという報告が出ています。最新の情報にリーチして、素早く対策を取ることができる選手は、パフォーマンス向上につなげることができます。月経とパフォーマンスの問題がつながらない選手は、受診というアクションにつなげるのも難しいと思います。
瀬田:自分の体で起きてることを「自分ごと」として捉えるのがすごく大切ですね。ビジネスでも周りで起こっていることや、任された仕事を「自分ごと」にできるかできないかで仕事のパフォーマンスが大きく変わります。特にスポーツは競技寿命が限られているので、自分のことをより理解できている方が、自分の体、そして人生とも上手くつき合っていけるのだと実感します。
能瀬氏:自分の体と向き合うきっかけがあるかどうかも大きいと思います。例えば、生理痛が強くて試合に出られなかった経験があれば、改善しようと考えますよね。きっかけがない場合は、本来なら学校教育でそれなりの知識を学ぶべきですが、今の学校教育では十分とは言えません。10代のうちに、正しい情報をどこで学ぶかというのは、さまざまな場で議論されています。
自分の成長は、目の前にある課題と日ごろの学びから
瀬田:能瀬さんが今の仕事の中で、成功体験だと感じたことや、スポーツと産婦人科医という切り口から業界を盛り上げられたと成長実感を持つことができた出来事はありますか?
能瀬氏:スポーツの分野は、医学界よりも多方面との連携が必要で、専門家や企業、さまざまな団体と連携する機会が多く、いろいろなことを学べたと思います。でも、根本にあるのは、「女性アスリートを医科学的にサポートし、健康を守りつつパフォーマンスを向上させたい」という想いです。 一つの方向に向かって、さまざまな分野の人々や団体と協力しながら進めていくのは面白いですし、とてもやりがいがあると思っています。
瀬田:能瀬さんご自身も学び続けているし、関わる人たちも常に自分を磨き上げているからこそ、進化し続けていけるのですね。

能瀬氏:私は「何年後の目標は持たない」と決めています。幸い、選手から診療というものを通して、課題や実際に選手たちが抱えている現場の問題を直接、伺うチャンスがあります。現場の問題を解決するということは、自分が大切にしている部分だったので、今後も全うしていきたいという思いはあります。時代の流れや風潮は変わっていくものなので、新しい課題にも常に向き合っていきたいです。
瀬田:現場というのがキーワードですね。現場に影響があるかどうかで「自分ごと」としての結びつき方も変わってくるし、その解釈も大きく変わると思います。能瀬さんのこだわりは、本当に意義深いですね。
能瀬氏:現場に寄り添うことは楽しいですね。診療に来た際に、知見とデータを示して根拠を示せるのと、なんとなく言うのとでは、選手の受け入れ方が全然違います。10年前は、選手のデータも今ほどなく、状況もわかりませんでした。だから課題も見えず、スポーツ界も産婦人科医も、女性のアスリートの問題をクローズアップしてきませんでした。産婦人科医として道を決めてからは、女性アスリートとの関わりの中で、自分がやるべきことを見出してきた瞬間の連続だったと思います。
瀬田:出会いやタイミングもあったかと思いますが、これが自分のやることだと思えた瞬間というのは、能瀬さんのキャリアにとって岐路だったのですね。
能瀬氏:こんなにどっぷりと、のめり込むとは思っていませんでした。今はもう腹をくくってやっていこうという思いですが、産婦人科とスポーツ医学の両者の知識をアップデートしながら関わり続けていくことが重要だと思っています。
次の世代にバトンを渡し、風を入れ替えることで組織が変わる
瀬田:スポーツ界は、トップダウンの文化がまだまだ根強い印象があります。良いアイデアを持っていても、上層部の承認が得られずに普及しないということもあるのではないでしょうか。スポーツ医学が広がる過程で、スポーツ特有の組織文化がボトルネックになっている部分はまだありますか?
能瀬氏:今まさに、変わってきているところかなと思います。世代交代が進み、若手へとバトンが渡りつつあります。スポーツ庁が競技団体のガバナンスコードを策定し、理事の任期や外部人材、女性の登用割合を明確にしたこともすごく大きいです。企業よりもスポーツ界の方が、女性役員の割合が高くなっているのではないでしょうか。スポーツ界が企業のモデルになって欲しいですね。
瀬田:一般企業よりも、スポーツ界の方が積極的に変わろうとしているのかもしれませんね。
能瀬氏:スポーツ界は医学をはじめ、多くの分野が深く関わり合っています。専門家や他の団体の取り組みを参考にしながら改善を進める中で、外部からの情報を得て、風通しが良くなっているのだと思います。
瀬田:業界の風を入れ替えていくことも重要でしょうし、素早く次の世代にバトンを渡せるかどうかは本当に大事ですよね。気持ちの良い選択ができるリーダーが組織の未来を作っていくのだと思います。

「明日生きているか分からない」だからこそ、目の前のことを着実にやっていきたい
瀬田:これまでの能瀬さんのお話しからは、タイミングの重要性や、学び続けてアップデートしていくことの大切さを改めて実感しました。未来に向けて実現したいことや、展望はありますか?
能瀬氏:正直なところ、あまり先のことは深く考えていません。実は私自身、くも膜下出血を経験しており、「明日生きているか分からない」という感覚が常にあります。だからこそ、目の前のことを着実にやっていきたい。本当にそれだけですかね。さまざまな人と関われば、関わるほど、多くの助言や情報が入ってきますが、自分の価値観や倫理観は崩したくないと思っています。
今の施設は、スポーツ界の中央組織としての役割を担っているので、組織内だけでなく、世界の状況にも目を向けないといけません。特に女性アスリートに関する課題については、日本と海外で状況を比較しながら、遅れを取らないようにしていく必要があると思っています。
瀬田:連携や協働がキーワードとして一貫していますね。外部とつながりながら、自分の価値観を大切にしつつ、確実に目の前のことをやり遂げるという姿勢を感じます。
能瀬氏:目の前の診察を通して、いろいろな競技の選手から学びながらここまでやってきました。選手は教科書であり、課題を私に提示してくれる存在です。だからこそ、臨床研究や自分が取り組んでいることが、現場と乖離しないように心掛けていきたいなと思います。
瀬田:選手の存在が能瀬さんの原動力なのですね。大きな取り組みと、一人ひとりの選手を結びつけていくことが、能瀬さんが歩む道の原動力になっているのだなと痛感しました。ビジネスの考え方とも共通点が多く、まさに能瀬さんらしいリーダーシップが詰まった大変興味深いお話でした。本日は貴重なお時間をいただき本当にありがとうございました。
コラム
Column
各サービスについての資料請求はこちら
Download documents
各サービスや講演、取材についての
お問い合わせはこちら
お問い合わせはこちら
Contact